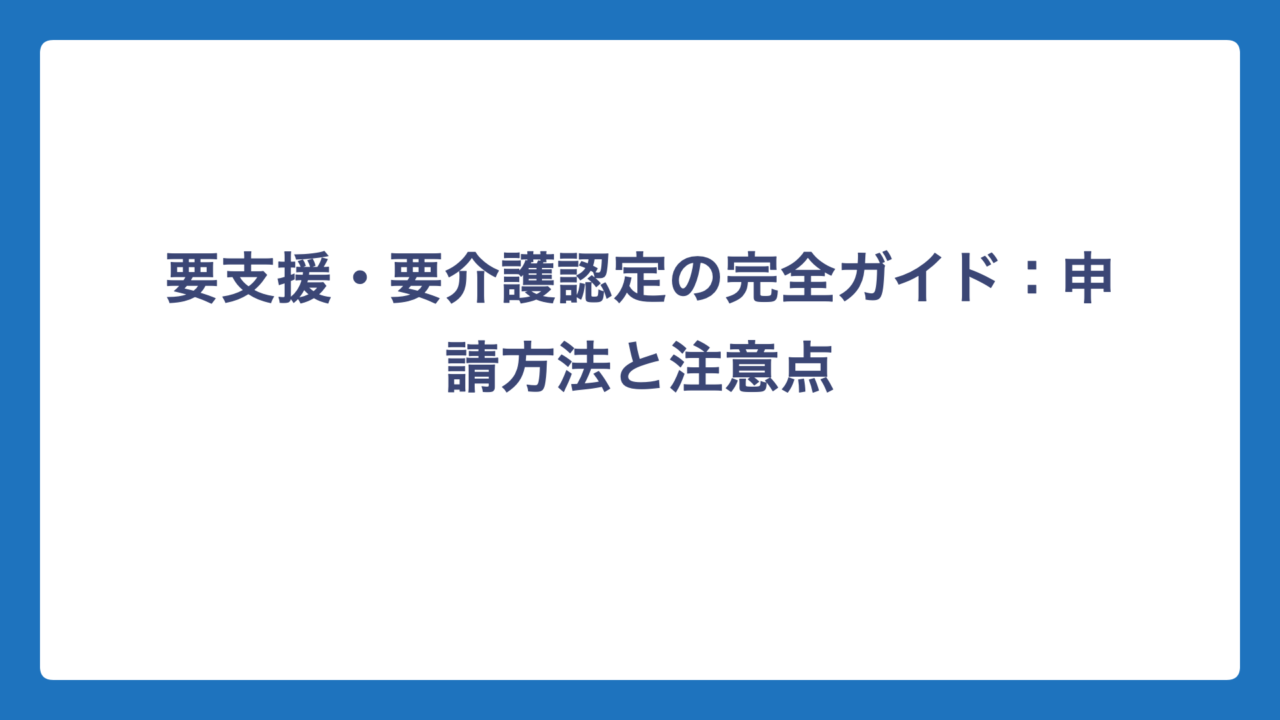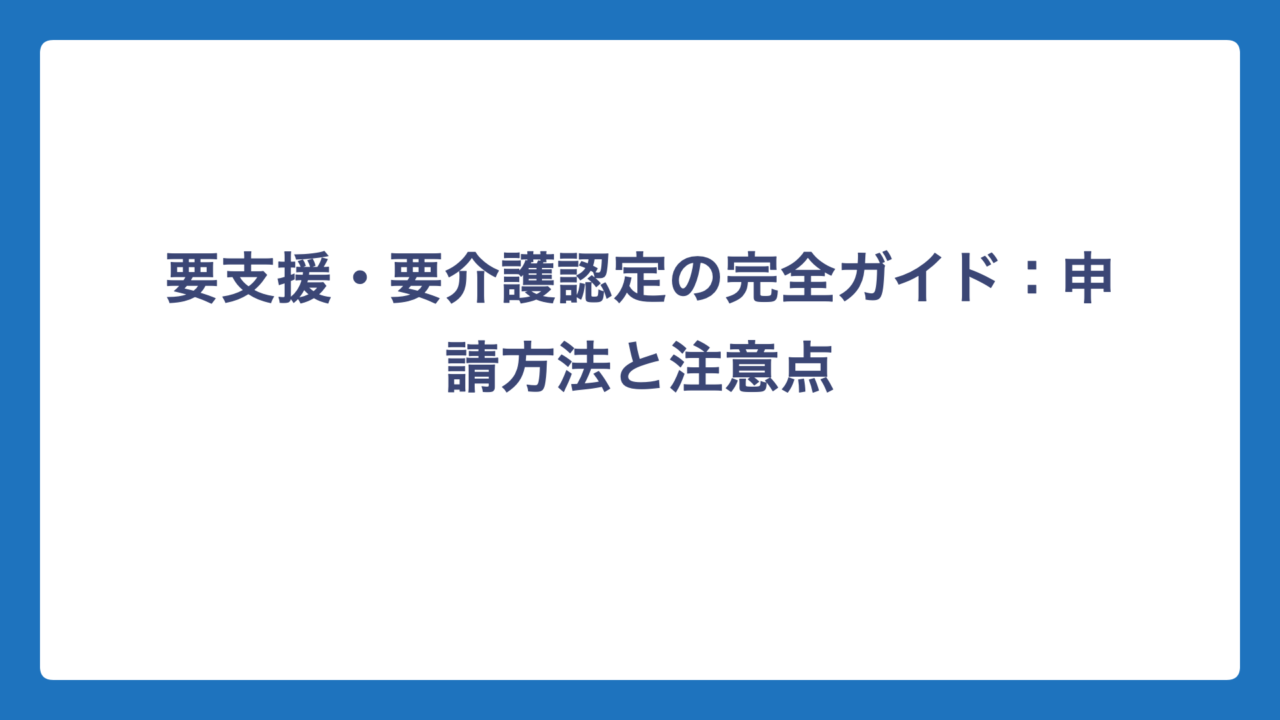要支援・要介護認定とは?
要支援・要介護認定は、介護保険サービスを受けるために必要な手続きです。介護保険と医療保険は異なるため、混同しないよう注意しましょう。
要支援・要介護認定の申請方法
家族が介護保険サービスを必要とする場合、以下の手順で申請を行います。
介護保険申請書の取得
- 住んでいる市役所の窓口で申請書を取得(市役所のホームページでもダウンロード可)
- 本人が記入(難しい場合は家族が代筆可)
- 家族が申請に行けない場合、地域包括支援センターやケアマネージャーに提出代行を依頼可能
申請後の流れ
- 市役所が病院の担当医に意見書を依頼
- 調査員が家庭訪問し、心身状態を調査
- コンピューターによる判定後、介護認定調査会で決定
- 申請から30日以内に認定結果が通知
- 認定結果に不服がある場合、60日以内に不服申し立てが可能(ただし、数ヶ月かかることも)
介護保険サービス利用にあたって
ケアマネージャーの探し方
- 要支援の人:地域包括支援センターが担当
- 要介護の人:地域包括支援センターや介護保険課が事業所を紹介 → その中からケアマネージャーを選択
認定前にサービスを利用したい場合
申請から結果が出るまで約30日かかるため、すぐに介護サービスを利用したい場合は、地域包括支援センターに相談し、ケアマネージャーに暫定プランを作成してもらうことで、申請日からサービスを受けられます。
※ ただし、暫定プランより低い介護度が認定された場合、自己負担額が増える可能性があるため注意が必要です。
要支援・要介護の区分ごとのサービス
要支援・要介護の区分により、利用できるサービスの上限額が異なります。
| 区分 |
介護サービス利用限度額 |
1割負担の場合の自己負担額 |
| 要支援1 |
約5万円(5000単位) |
約5000円 |
| 要介護5 |
約36万円(36000単位) |
約36000円 |
※ 単位数や金額はおおよそであり、収入によって2割、3割負担になる場合があります。
介護保険の加入について
介護保険の対象者
- 40歳から64歳(第2号被保険者):各種医療保険から天引き
- 65歳以上(第1号被保険者):原則として年金から天引き
介護被保険者証について
- 65歳以上:市区町村から自動で郵送される
- 40歳~64歳:16の特定疾病に該当し、介護認定を受けると発行される
介護保険の16の特定疾病
以下の16種類の特定疾病に該当する場合、40歳以上でも介護保険サービスを受けることができます。
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症
- 関節リウマチ
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 多系統萎縮症
- がん末期
- 筋萎縮性側索硬化症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
- 閉塞性肺血管疾患、閉塞性動脈疾患
- 両側の変形性膝関節症・股関節症
覚え方:「パセリ残したガキ外へ」
パーキンソン病関連疾患
セ関節リウマチ
リ脊髄小脳変性症
残脳血管疾患
し初老期の認知症
た多系統萎縮症
ガがん末期
キ筋萎縮性側索硬化症
外閉塞性肺血管疾患
まとめ
- 要支援・要介護認定は、介護サービスを受けるための重要な手続き
- 申請から結果が出るまで約30日かかるため、早めの申請が大切
- 暫定プランを活用すれば申請日からサービス利用可能(ただしリスクあり)
- 要支援・要介護の区分によって利用限度額が異なる
- 40歳から介護保険に加入し、特定疾病があれば64歳以下でも介護サービスを受けられる
介護の現場で役立つ知識を共有し、一緒に学んでいきましょう!