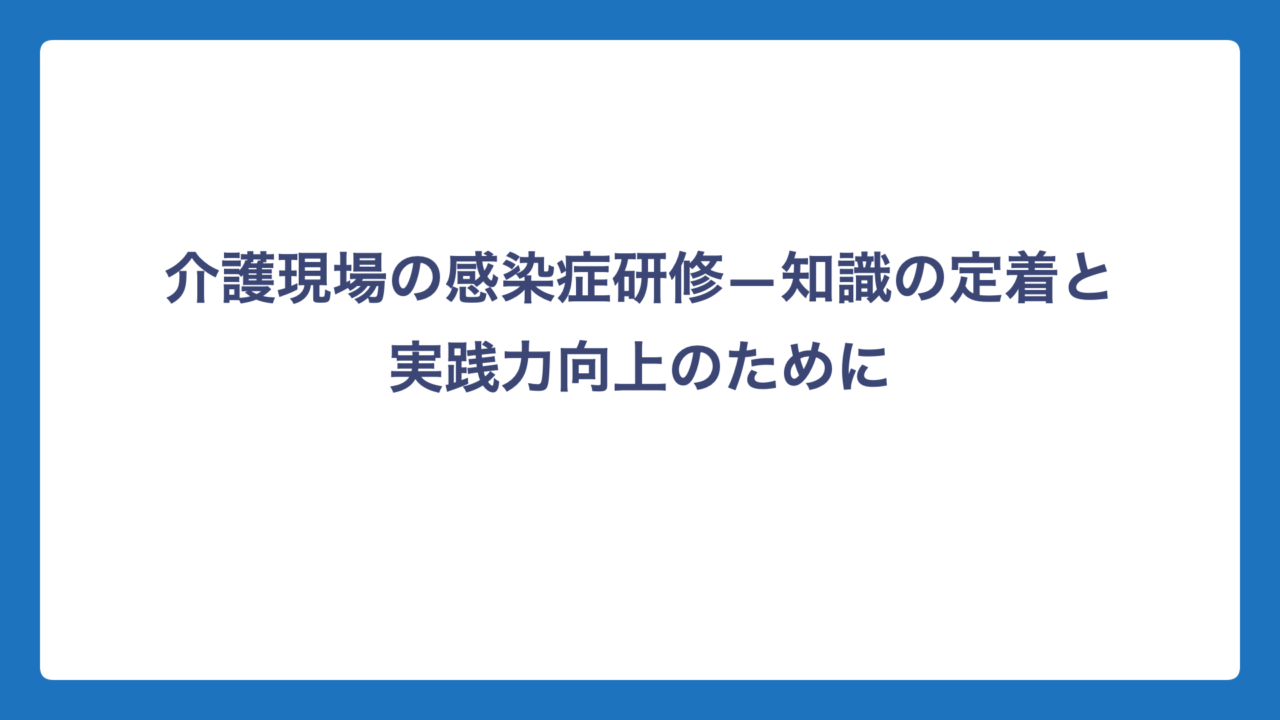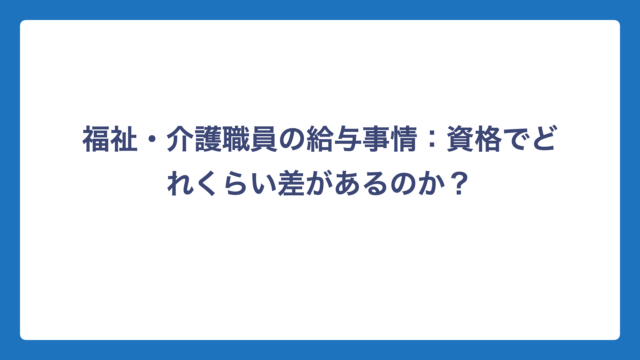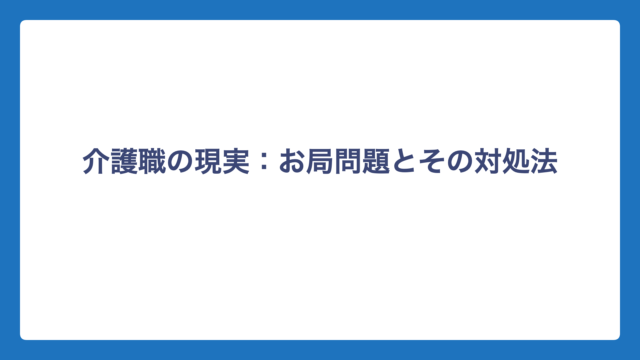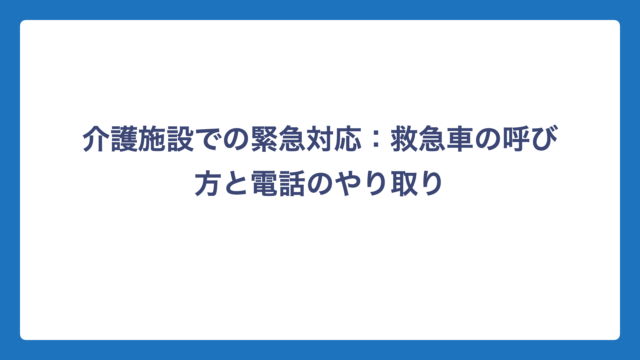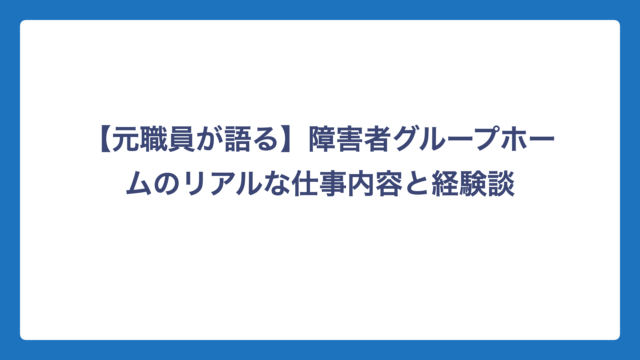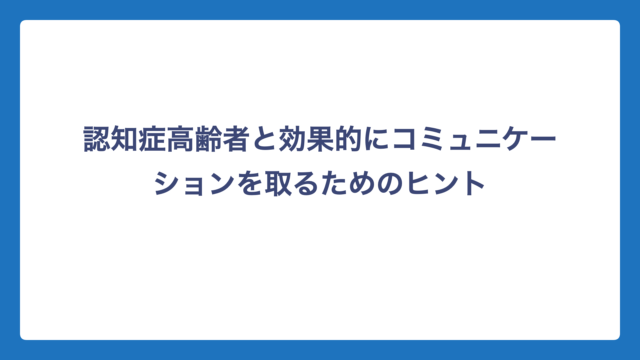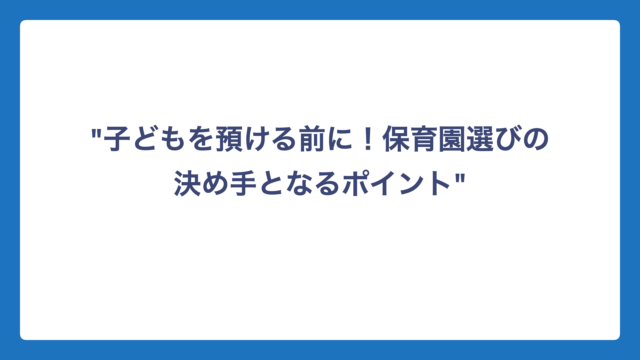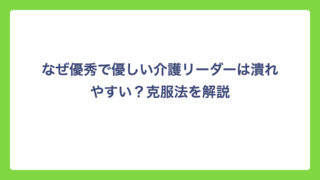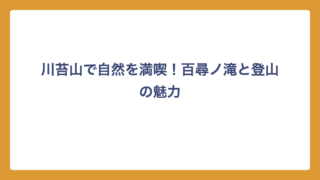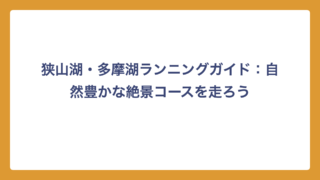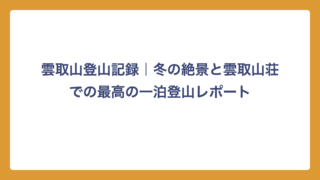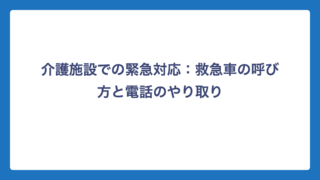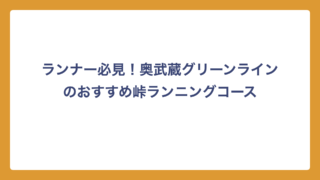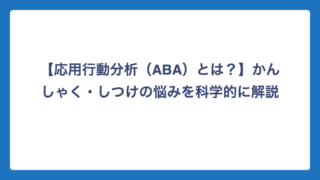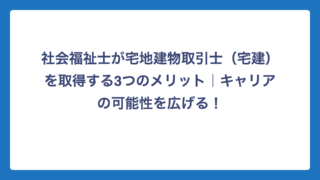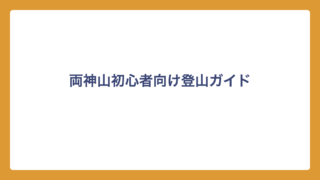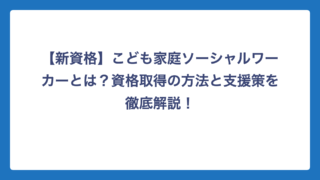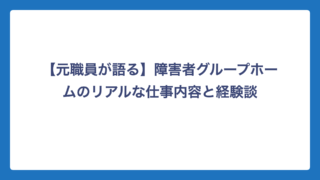介護現場の感染症研修―知識の定着と実践力向上のために
介護の現場における感染症対策は、職員の安全と利用者の健康を守るために不可欠です。しかし、研修を受けても実際の知識や対応力が十分に備わっていないと感じることが少なくありません。特に、感染経路(接触感染、飛沫感染、空気感染、血液媒介感染)や、具体的な感染症(B型・C型肝炎など)の感染ルートについての理解が課題となっています。本記事では、効果的な感染症研修のあり方について提案します。
知識の定着と実践力向上のための改善策
1. インプットとアウトプットのバランスを取る
知識を定着させるためには、受動的な学び(インプット)だけでなく、能動的な学び(アウトプット)も重要です。
- 研修前の準備:事前に資料と問題集を配布し、研修の内容を予習できる環境を整える。
- 研修中の確認:学んだ内容を即座に確認できるように、研修の終わりに理解度テストを実施。
- グループディスカッション:間違いや疑問点を参加者同士で話し合い、職員の理解を深める。
- フィードバックの充実:講師や管理者がテスト結果や質問への解答を即座に行い、知識の定着を図る。
このような仕組みを導入することで、新人職員の現場適応力が向上し、再教育の負担が軽減されます。
2. 実際の対応を練習する
知識だけではなく、実践的な対応力を高めることも不可欠です。そのため、感染症発生時の対応を、マニュアルに沿ったシミュレーション形式で学ぶことが効果的です。
- 実技訓練:感染症対策の手順を実際に実践(例:個人防護具の着脱、手洗い、消毒方法)。
- ロールプレイング:感染が発生した場面を想定し、対応策を体験。
- 評価と改善:演習後に振り返りを行い、改善点を共有。
特に新人職員にとって、マニュアルを読むだけでなく、実際に身体を動かして学ぶことが、より効果的なスキル習得につながります。
3. 具体的な事例を研修に組み込む:ノロウイルス対策の例
ノロウイルスは介護現場において特に注意が必要な感染症の一つです。以下のような実践的な対策を研修で学ぶことが重要です。
感染拡大防止のキーポイント
- 少人数での対応:感染拡大を防ぐため、最小限の職員で処置を行う。
- 個室での隔離:感染者を速やかに隔離し、接触者を制限。
- 効果的な換気:空気感染のリスクを減らすために定期的な換気を徹底。
- 適切な消毒方法:次亜塩素酸ナトリウム(ハイター等)を使用し、環境表面を消毒。
- 個人防護具(PPE)の正しい使用:マスク、手袋、ガウンの正しい着脱方法を訓練。
- 適切な手洗い技術:アルコール消毒ではなく、石鹸と流水による手洗いを徹底。
これらの対策を実際の事例をもとに研修で学ぶことで、感染発生時に迅速かつ効果的に対応できるようになります。
感染症研修の重要性と今後の展望
介護現場における感染症研修は、単なる知識習得ではなく、実際に危機が発生した際に職員が冷静かつ適切に対応できる能力を養うことが目的です。
- 職員の感染予防意識の向上:知識だけでなく、日常的な感染対策を習慣化。
- 施設全体の安全性の向上:正しい対応が徹底されることで、感染拡大のリスクを低減。
- 職員間の連携強化:実技研修を通じて、職員同士の協力体制が向上。
今後も、より実践的で効果的な研修を導入し、職員のスキルアップを図ることが求められます。感染症対策の強化は、職員と利用者の命を守るための重要な取り組みであり、継続的な改善が不可欠です。
スポンサーリンク