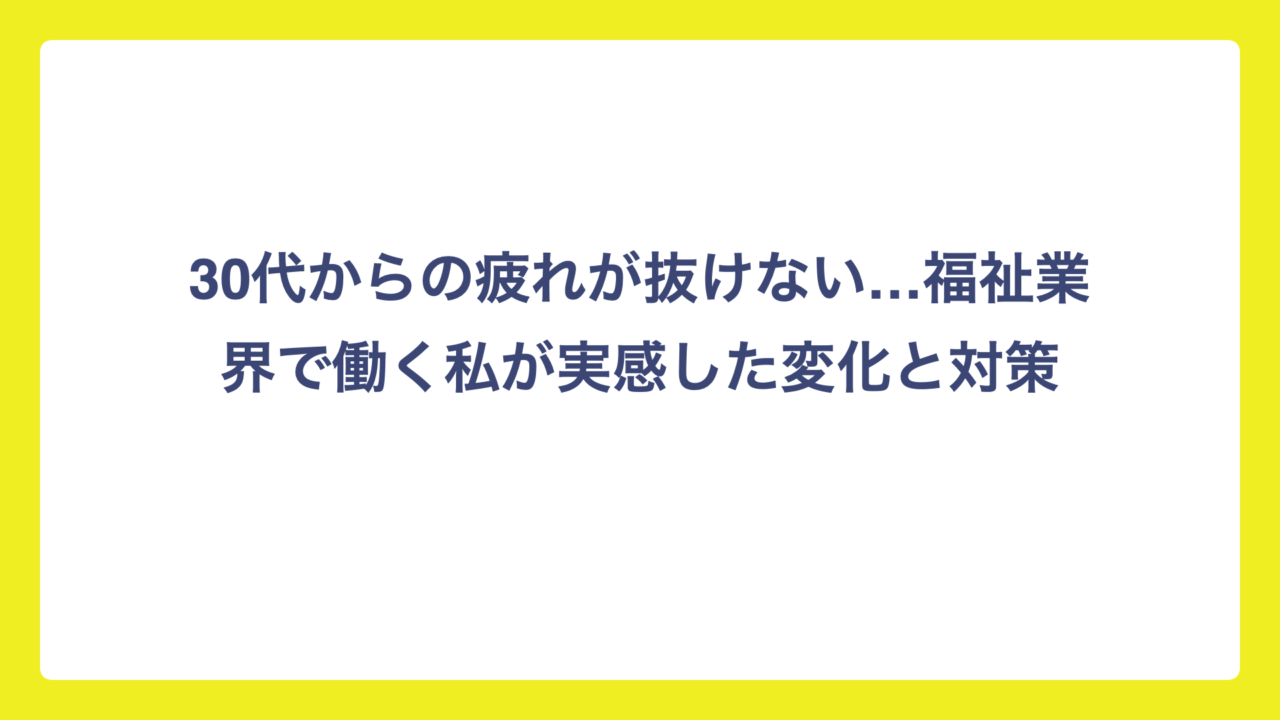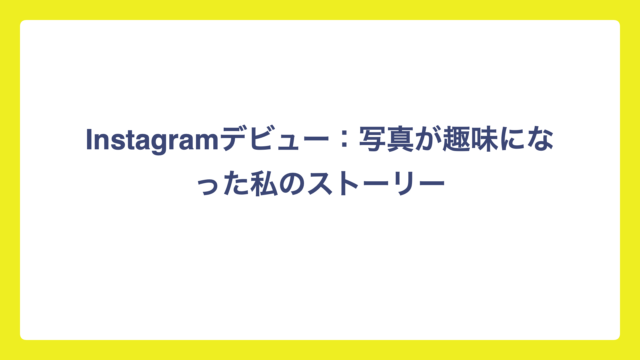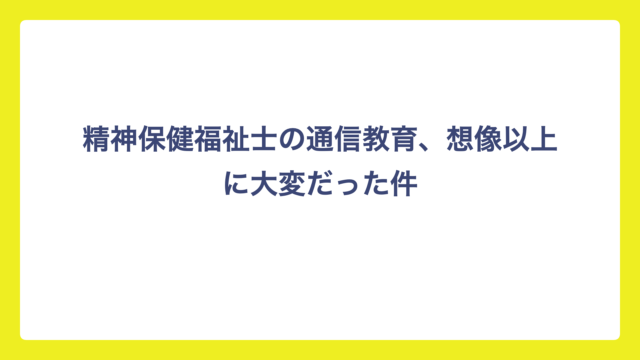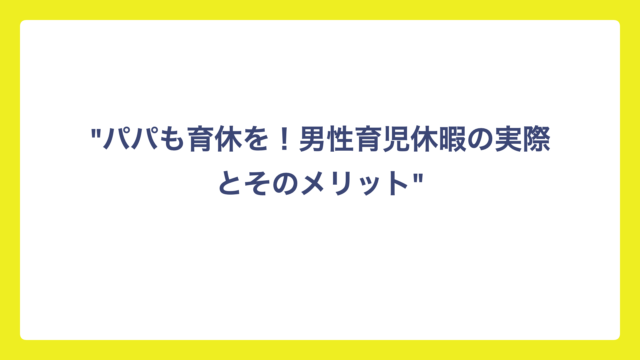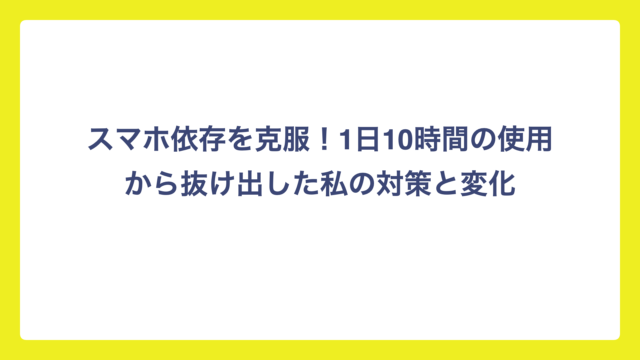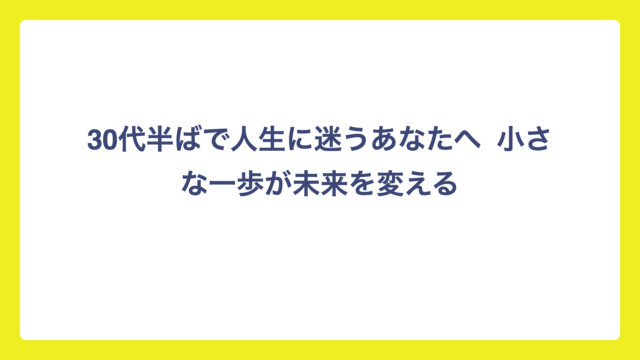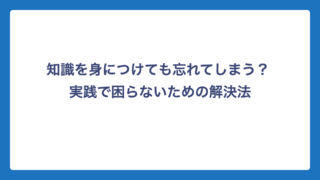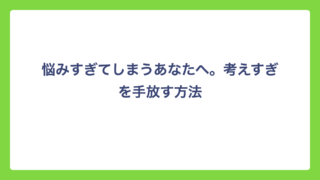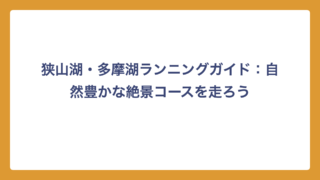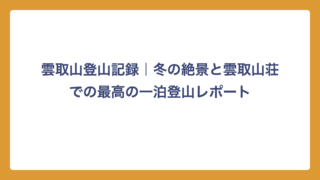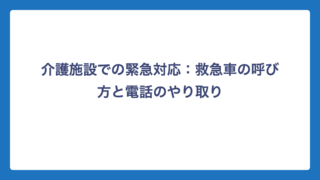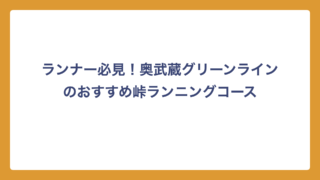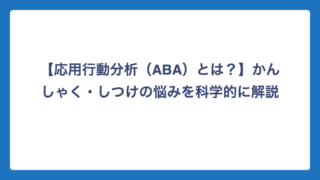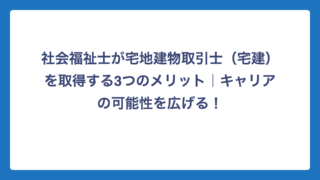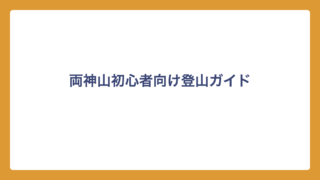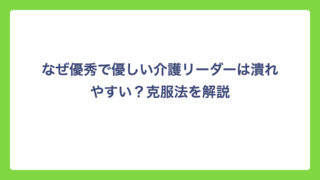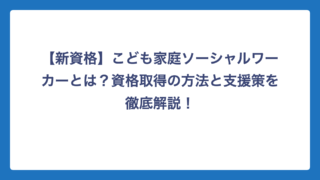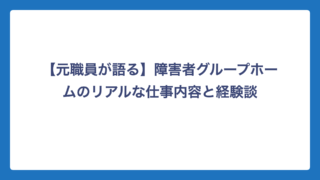はじめに
20代の頃は夜勤明けでもそのまま遊びに行ったり、多少の睡眠不足でも乗り切れたのに、30代になった途端、疲れが抜けにくくなったと感じませんか?
福祉業界で働く私は、夜勤や長時間労働が当たり前の生活を続ける中で、明らかに体の変化を実感しています。今回は、30代からの「疲れ問題」に焦点を当て、私が実際に感じた変化と対策についてお話しします。
1. 30代になって感じた「疲れ」の変化
20代の頃と比べて、30代に入ってから次のような変化を感じるようになりました。
✅ 飲酒量が増えたが、翌日に影響が出るようになった
→ 若い頃は少々飲みすぎても翌日は平気だったのに、今では翌日が潰れることもしばしば…。
✅ 短時間睡眠の後に目が覚めると、なかなか寝つけない
→ 夜勤後に寝ようとしても、途中で目が覚めるとそのまま寝られなくなることが増えた。
✅ 徹夜がとにかくしんどい
→ 20代の頃は「まあ何とかなる」と思っていたが、今は徹夜明けは体が鉛のように重い。
✅ 運転中の眠気が増えた
→ 以前なら気合で乗り切れたが、今は眠くなったら休憩しないと危険。
✅ 慢性的な疲労感がある
→ 仕事の疲れが抜けず、休日もダラダラ過ごしてしまう。
✅ 夜勤明けに遊びに行く気力がない
→ 以前は夜勤後にそのまま遊びに行けたのに、今は無理。体がついてこない。
こうした変化が積み重なると、「疲れが取れないのが普通」という状態になりがちです。でも、これは仕事のせいだけではなく、年齢とともに体の仕組みが変わっているからこそ起こること。
2. なぜ30代から疲れやすくなるのか?
年齢とともに疲れやすくなる原因はいくつかあります。
① 代謝の低下
30代に入ると基礎代謝が落ち、エネルギーの回復が遅くなります。そのため、20代の頃と同じ生活をしていても、疲れが抜けにくくなるのです。
② 睡眠の質の変化
加齢とともに睡眠が浅くなりやすくなります。特に夜勤のある仕事では、体内リズムが乱れやすく、疲労回復に必要な深い睡眠がとれなくなることも。
③ ホルモンバランスの変化
ストレスや生活習慣の影響で、疲労回復に関係するホルモン(コルチゾールや成長ホルモン)の分泌が変化。結果として、疲れが抜けにくくなります。
④ 生活習慣の影響
飲酒や食生活の乱れ、運動不足など、生活習慣が20代の頃と変わらないと、体がついてこなくなることも。
3. 30代からの疲労対策!私が実践していること
このまま「疲れやすい体」で過ごすのは嫌だったので、いくつかの対策を試してみました。
✅ 飲酒を減らし、休肝日を作る
→ 週に2〜3回はお酒を飲まない日を作ることで、翌日の疲れが軽減。
✅ 睡眠の質を改善する
→ 夜勤後はスマホを見ずにすぐ寝る、寝る前のストレッチや深呼吸を取り入れる。
✅ 短時間睡眠でも「休息の質」を上げる
→ 眠れなくても「目を閉じて横になる」だけで脳が休まることを意識。
✅ 運転時は眠気を感じたら無理せず休憩
→ カフェインを摂取し、短時間の仮眠をとる。安全第一!
✅ 運動を取り入れる(無理のない範囲で)
→ 夜勤前後に軽いストレッチやウォーキングをすることで、血流を良くし、疲労回復を促進。
✅ ダラダラすることを「悪」としない
→ 疲れたらダラダラしてもOK!自分を責めず、「休む時間」と割り切る。
4. 無理をしない!「自分のケア」も仕事のうち
福祉業界で働いていると、どうしても「人のケア」を優先しがち。でも、そのためには自分の体と心のケアも大切です。
✅ 若い頃と同じように動こうとしない
✅ 疲れたらちゃんと休む(ダラダラも必要)
✅ 生活習慣を少しずつ見直す(無理なくできることから)
この3つを意識するだけでも、30代からの「疲れ」と上手く付き合えるようになります。
まとめ
✔ 30代に入ると、疲れが抜けにくくなるのは「自然なこと」
✔ 体の変化を理解し、無理をしないことが大事
✔ 飲酒・睡眠・運動・休息の質を少しずつ改善すると楽になる
福祉の仕事は体力も気力も必要ですが、まずは自分の体を大事にすることが長く続けるためのコツ。無理せず、少しずつ改善していきましょう!
あなたは最近、「疲れが抜けにくくなったな」と感じることはありますか?
もし実感があれば、ぜひコメントやシェアで教えてくださいね!