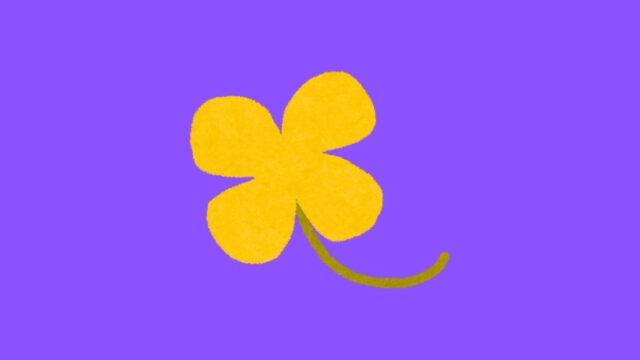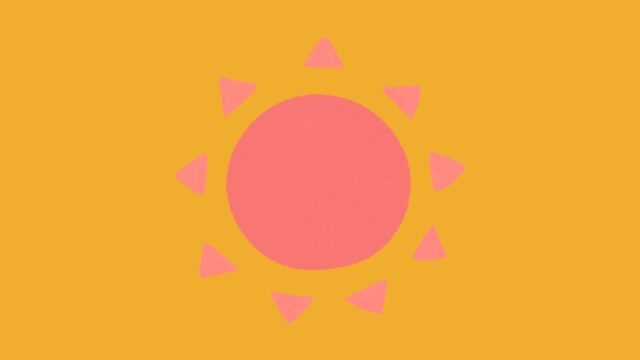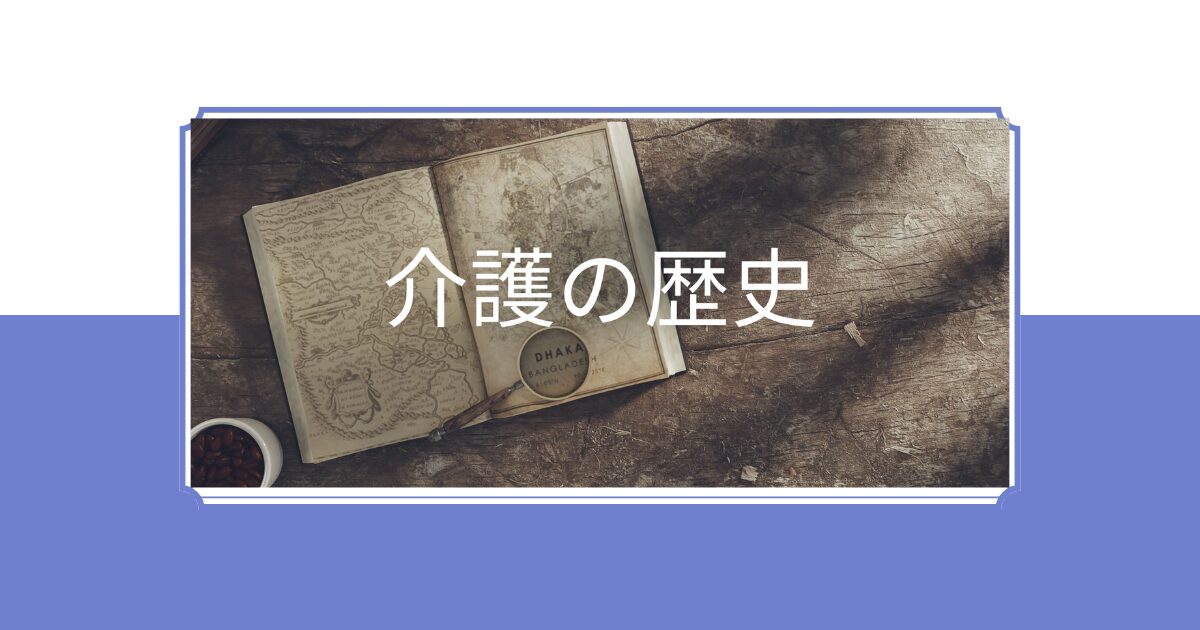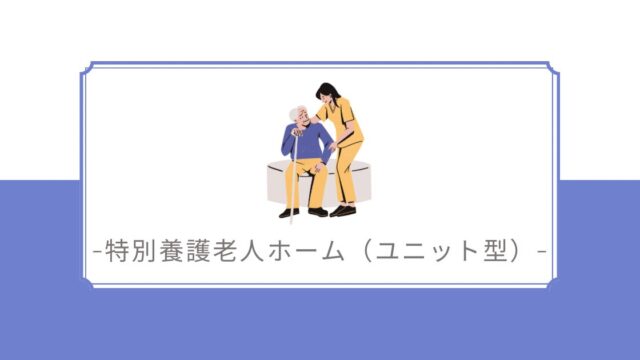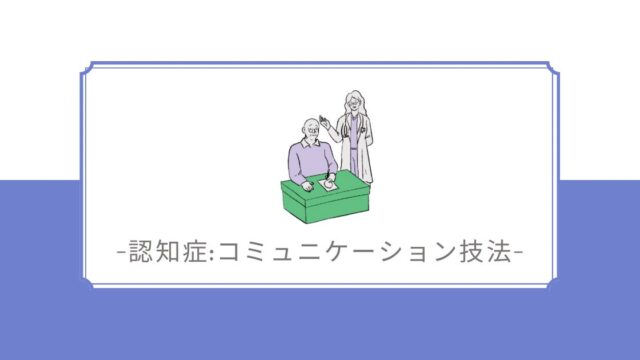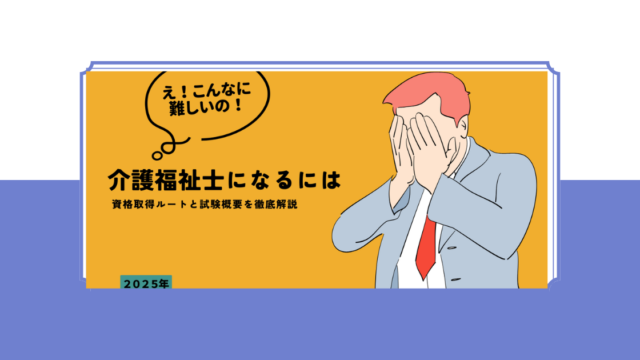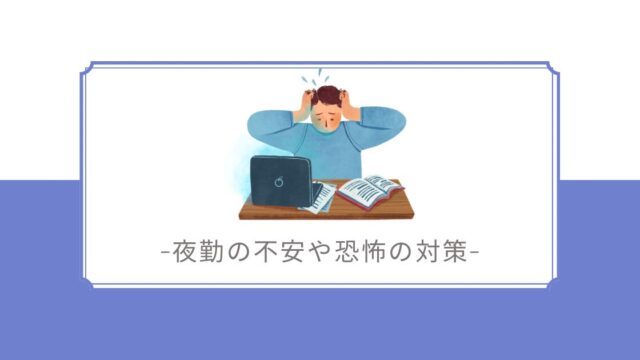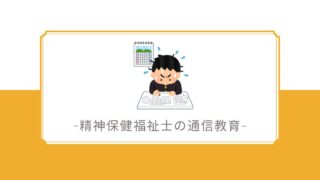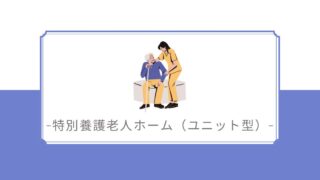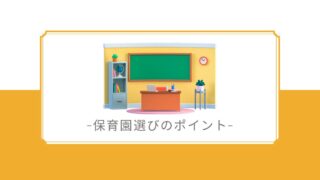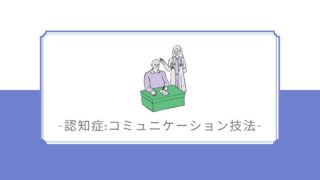はじめに|介護はいつから始まった?
今や当たり前のように聞く「介護」という言葉。しかし、介護という概念が日本社会に根付いたのは意外と最近のことです。
かつては家族が「当たり前に」担っていた介護も、時代とともに社会全体で支える仕組みへと変化してきました。
今回は、そんな日本の介護の歴史を振り返りながら、未来の介護がどうなっていくのかを考えてみましょう!
戦前の介護|家族が支える時代
「養老院」と「救貧」の時代(明治~戦前)
日本における「介護」の始まりは、明治時代にまで遡ります。当時は、病気や障害のある高齢者は家族が介護するのが当たり前で、国の福祉制度はほとんど存在しませんでした。
しかし、身寄りのない高齢者や生活困窮者のために、**「養老院」**という施設が設立されました。これは現在の特別養護老人ホームの前身とも言えます。
とはいえ、当時の福祉は「慈善事業」に近いものであり、介護=ボランティア的な支援という考え方が一般的でした。
戦後の介護|「福祉」としての制度化へ
1950年代:「家庭奉仕員」が誕生
戦後の日本では、戦争で家族を失った人々や貧困層への支援が課題となりました。この中で、高齢者向けの支援として1956年に**「家庭養護婦派遣制度」**(現在の訪問介護の前身)が誕生しました。
この制度は、家事や介護を手伝う「家政婦」のような役割を担っていましたが、「福祉」というよりは労働の一環としての位置づけでした。
1963年:「老人福祉法」の制定
1950年代までは、「介護は家族の責任」とされていましたが、高齢者人口の増加を受けて1963年に**「老人福祉法」**が制定されました。
これにより、
✅ 「養老院」が「老人ホーム」に進化
✅ 「家庭奉仕員」という職業が誕生し、公的な支援が開始
福祉施設の設立が国の施策に組み込まれる
といった変化が生まれました。
1980年代~1990年代|介護の専門職化と制度改革
1980年代:「介護」の概念が広がる
1980年代になると、日本の高齢化が本格化し、社会全体で介護を支える必要性が高まりました。この頃、「認知症(当時は痴呆症)」の高齢者が増え、医療と福祉の連携が課題になります。
また、国際的な流れもあり、「介護は専門職として確立すべきだ」という動きが強まり、1987年に**「社会福祉士及び介護福祉士法」**が制定され、介護の専門職化が進んでいきます。
1990年代:「介護保険」導入への準備
1990年代には、さらなる高齢化に対応するために**「介護保険制度」**の導入準備が進められました。
この時期には、
✅ 訪問介護サービスの拡大
✅ 特別養護老人ホームの増設
✅ 「認知症ケア」への関心の高まり
といった動きが加速していきます。
2000年~現在|介護保険制度の施行とデジタル技術の活用の波
2000年:「介護保険制度」がスタート
介護の歴史における最大のターニングポイントが**「介護保険制度」**の導入です。
それまでの「措置制度」(行政が入所を決める仕組み)から、**利用者が自らサービスを選ぶ「契約制度」**へと大きく転換しました。
✅ 介護サービスの拡充(訪問介護・デイサービス・グループホームなど)
✅ 「自立支援」の考え方が主流に
✅ ケアマネジャー(介護支援専門員)が登場
これにより、介護は「家族がするもの」ではなく、専門職と地域社会が支えるものへと変化しました。
未来の介護|デジタル技術の活用でどう変わる?
現在、日本の高齢化率は**29.0%(2023年)**を超え、介護の需要はますます高まっています。しかし、介護職員の人手不足が深刻化しており、今後の課題となっています。
その解決策として期待されているのがデジタル技術の活用です。
介護の未来を変える3つのポイント
✅ 介護ロボットの普及
- 自動排泄支援機器、移乗サポートロボットの導入
- 介護者の負担軽減に貢献
✅ AIとビッグデータの活用
- 認知症の進行予測や介護プランの最適化
- 介護記録の自動作成で業務の効率化
✅ オンライン介護の拡大
- 遠隔診療やオンライン介護相談の普及
- ICT(情報通信技術)を活用した見守りシステムの導入
【まとめ】介護は「支援するもの」へと進化し続ける!
📌 戦前~1960年代:「家族が介護する時代」
📌 1980年代:「介護の専門職化が進む」
📌 2000年以降:「介護保険制度で大きく変化」
📌 2020年代以降:「デジタル技術の活用で新たな介護の形へ」
介護は、単なる「お世話」ではなく、**「その人らしい生活を支えるもの」**へと進化しています。
そして、今後もテクノロジーと人の力を融合させた介護が求められる時代になっていくでしょう。
これからの介護の未来を、一緒に考えていきませんか?