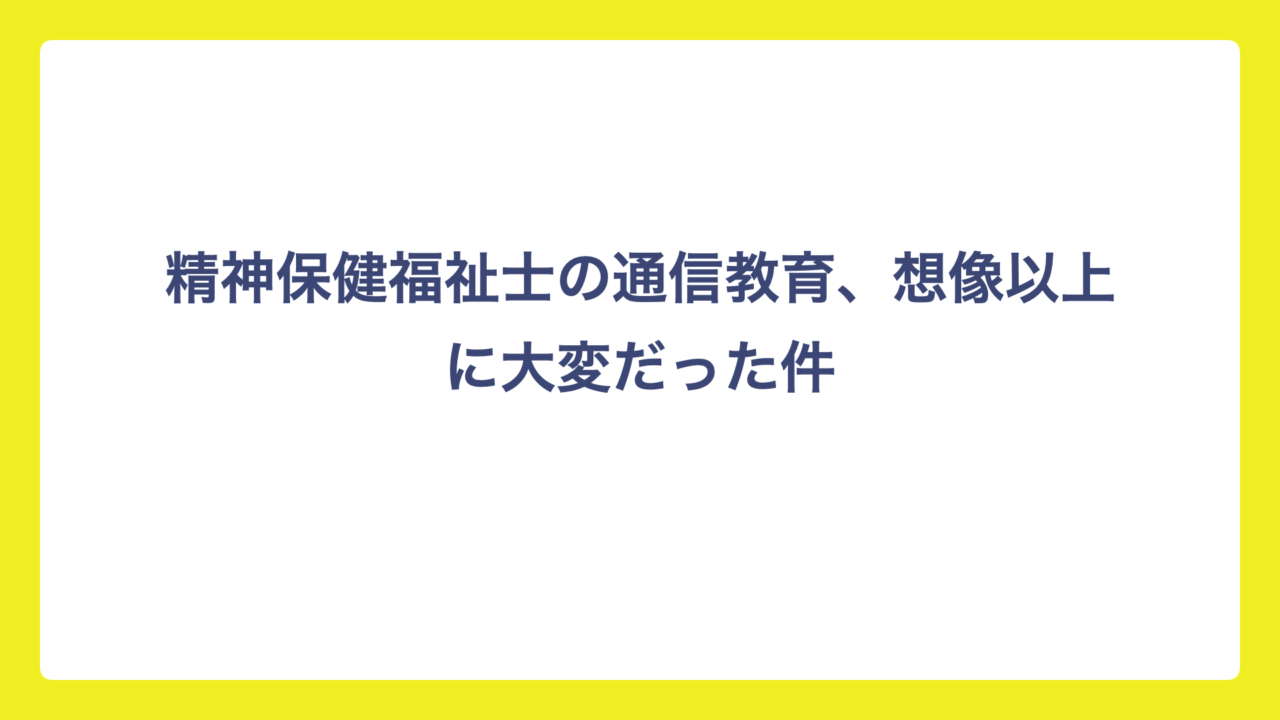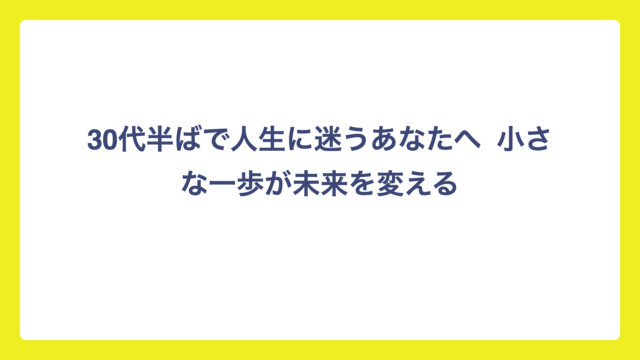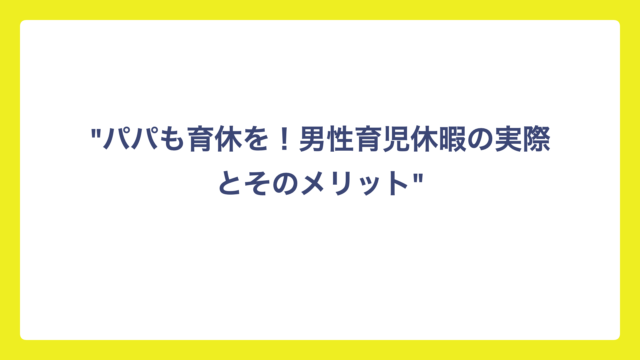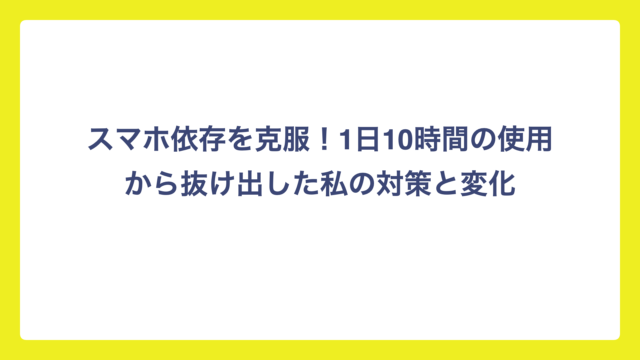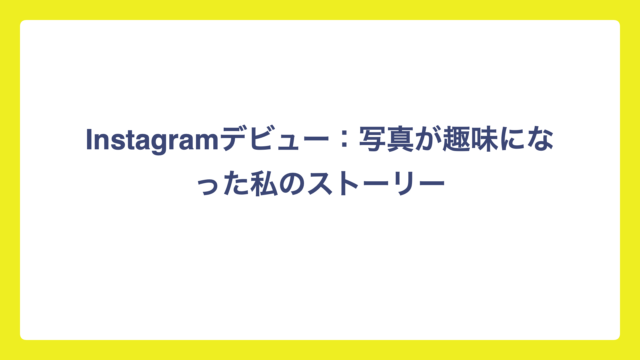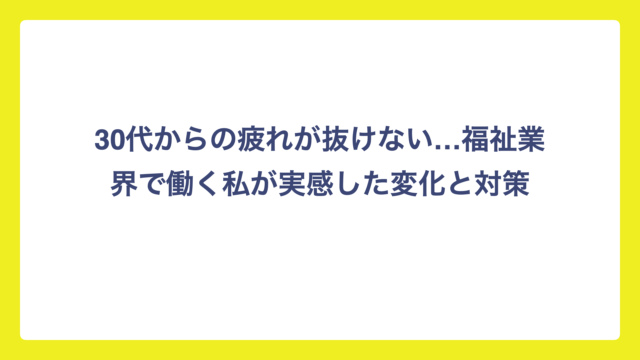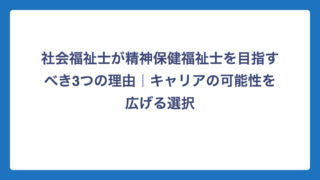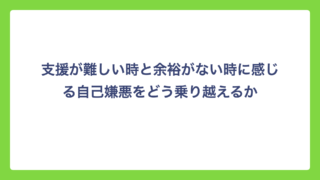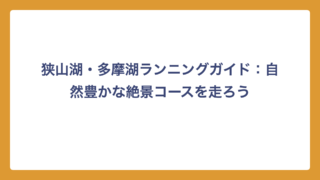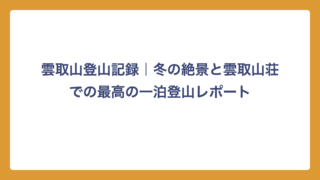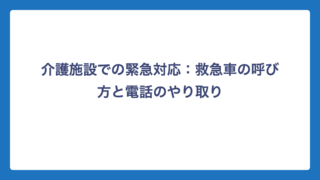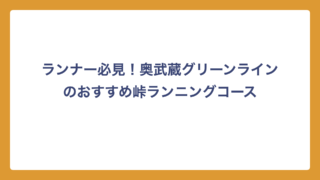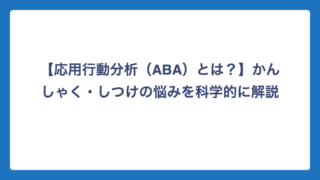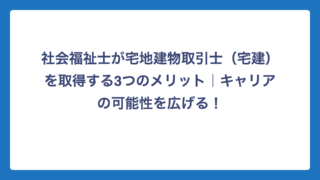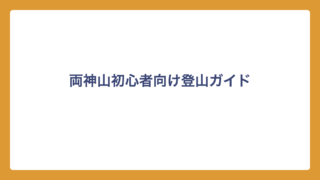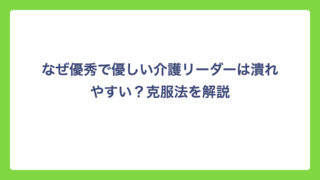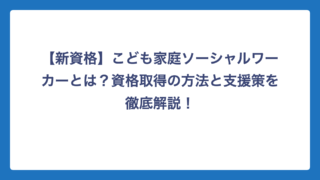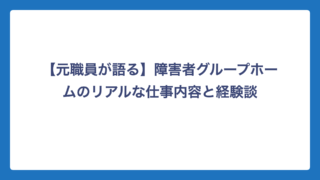〜短期集中&超直前講座で国家試験に合格できた理由〜
こんにちは、ナックです。
福祉業界で働きながら、2児の育児にも奮闘中のアラサー男です。
2025年2月の第27回 精神保健福祉士国家試験に合格しました!
ですが、ここまでの道のりは想像以上にしんどかった…。
特に通信教育との両立は、本気で計画と工夫が必要でした。
今回は、**短期集中の勉強法+直前期に受講した「超直前講座」**が合格の決め手になった私の体験談をお届けします!
1. 通信教育は、甘く見てたら痛い目見る件
-
✅ 5月・7月・9月:確認テスト&レポート提出
-
✅ 6〜9月:スクーリング(毎月1〜2回)
仕事+育児の中、このスケジュールをこなすのは本当に大変でした。
「通信=自分のペース」と思っていたら、完全に裏切られました。
2. 私が選んだのは「短期集中+スキマ活用」
長期戦は無理と割り切って、「3か月集中戦略」に切り替え。
時間のない人間には、これが一番合っていました。
■ 実践した勉強スタイル:
-
毎日30分〜1時間のスキマ学習をルーティン化
-
市販の過去問を3周以上。間違いノートを作って復習
-
YouTubeや音声講座で“ながら勉強”も活用
3. 家族の支えがなければ無理ゲーだった
子どもが小さい中での挑戦。
夜や休日は、パートナーに家事・育児をお願いしながら時間を捻出しました。
協力してもらえる環境があるなら、遠慮せず甘えるのがコツ。
4. 直前期は「超直前講座」で一気に仕上げ!
独学だけでは不安だった私は、試験の1か月前に「超直前講座(オンライン)」に申込。
これが想像以上に良かった!
-
重要ポイントが絞り込まれていて、復習に最適
-
出題傾向の変化や注意すべき分野を丁寧に解説
-
講師の「ここは出る!」の言葉が的中した問題も!
自分ひとりでは見落としていたであろう分野に気づけたことで、最後の1点・2点を積み上げられた感覚がありました。
5. 合格のカギは「完璧じゃなくて、継続と戦略」
寝落ちした日もあれば、予定通りに勉強が進まない週もありました。
でも、“やめなかった”ことが最大の勝因だと思っています。
そして「どこに力を入れて、どこは捨てるか」を決められたのは、
超直前講座での情報と整理のおかげでした。
◆まとめ:通信教育、マジで大変。でも、戦略次第で勝てる。
-
通信教育は自由なようで超ハード。自己管理がすべて
-
短期集中&過去問中心が効果的
-
直前期は外部講座で“仕上げ”するのも賢い選択肢
これから受験する皆さんへ。
時間がなくても、完璧じゃなくても、合格できます。
自分なりのやり方で、無理なく続けること。
そして不安なら、プロの力も遠慮なく借りましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
同じように頑張っている方の参考になれば嬉しいです。応援しています!